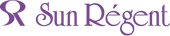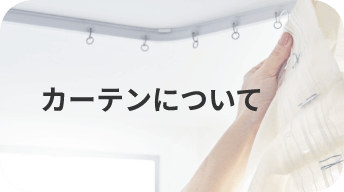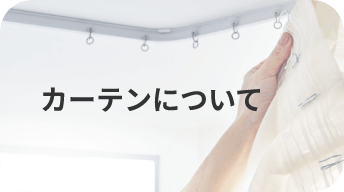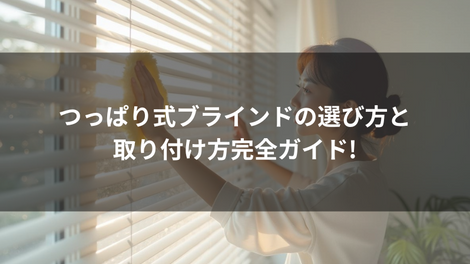Contents
賃貸物件に引っ越したばかりの方、窓周りの目隠し対策に悩んでいませんか?カーテンやブラインドを付けたいけれど、壁に穴を開けられない…。そんなお困りの方も多いのではないでしょうか。
「部屋が丸見えで、早く目隠しを付けたいけど、壁に穴を開けたら退去時に修繕費用がかかりそう…」「カーテンレールがないのに、どうやって取り付ければいいの?」といった声をよく耳にします。
そんな時におすすめなのが、つっぱり式ブラインドです。壁に穴を開けずに設置できるので、賃貸物件でも安心して使用できます。
つっぱり式ブラインドは種類も豊富で、お部屋の雰囲気や予算に合わせて選べます。ただし、正しい選び方や取り付け方を知らないと、後々トラブルの原因になることも。
この記事では、つっぱり式ブラインドの基礎知識から選び方、取り付け方、お手入れ方法まで詳しく解説していきます。賃貸でも簡単に取り付けられる、つっぱり式ブラインドの魅力を知っていただき、快適な窓周りづくりのお役に立てれば幸いです。
つっぱり式ブラインドとは

つっぱり式ブラインドは、窓枠の上部を専用の突っ張りで固定して設置する新しいタイプの窓装飾アイテムです。壁に穴を開ける必要がないので、賃貸物件での使用に最適な商品となっています。
従来のブラインドと同じように光や視線をコントロールできる機能を持ちながら、*工具を使わずに誰でも簡単に取り付けられる特徴があります。設置時は突っ張り棒の力で固定するため、賃貸物件の退去時にも跡が残らず、原状回復費用を気にする必要がありませんよ。
つっぱり式ブラインドのメリット・デメリット
つっぱり式ブラインドは、工具不要で設置できる手軽さと、賃貸物件での使いやすさが最大の特徴ですが、それぞれ良い点と気をつけたい点があります。
メリットの第一は、壁に穴を開けずに設置できるという点です。賃貸物件での原状回復費用を気にせず、自由に窓装飾を楽しむことができますよ。また、取り付けや取り外しが簡単なので、模様替えの際にも便利です。さらに、専門業者に依頼する必要がないため、設置費用を抑えられるのも魅力的ですね。
一方で、デメリットとしては安定性に若干の不安がある点に注意が必要です。突っ張り棒の力だけで固定するため、重いタイプのブラインドは使用できません。また、窓枠のサイズや形状によっては設置できない場合もあるでしょう。地震や強風時には揺れやすいため、振動対策用のストッパーを併用することをおすすめします。
価格面では、通常のブラインドと比べてやや割高になる傾向にあります。これは突っ張り式の特殊な構造による製造コストが影響しているためです。ただし、業者への取り付け費用が不要なため、トータルコストで見ると大きな差はありませんよ。
つっぱり式ブラインドは確かに制限もありますが、手軽さと機能性を兼ね備えた、賃貸物件に最適な窓装飾アイテムといえます。設置場所や使用環境をよく確認して、自分に合った製品を選んでみてください。
壁に穴を開けないブラインドの種類
壁に穴を開けないブラインドには、つっぱり式以外にもいくつかのタイプがあります。それぞれの特徴を理解して、お部屋の条件に合った最適な商品を選びましょう。
主なタイプとして、まず突っ張り棒タイプが挙げられます。窓枠の上部に専用の突っ張りを設置し、ブラインドを取り付けるシンプルな構造です。最も一般的で、取り付けも簡単なため、初めての方におすすめできます。
次に、吸盤式ブラインドがあります。窓ガラスに直接吸盤で固定するタイプで、窓枠のないお部屋でも設置可能です。ただし、ガラスの表面状態によって吸着力が変わるため、事前に確認が必要でしょう。
マグネット式も便利な選択肢の一つです。スチール製の窓枠やドアに磁石で固定できますが、取り付け面が限定されるという特徴があります。オフィスのパーティションなどによく使用されていますよ。
| タイプ | 特徴 | 適している場所 |
|---|---|---|
| つっぱり式 | 安定性が高く汎用性あり | 一般的な窓枠 |
| 吸盤式 | 窓枠不要で直接設置可能 | フラットなガラス面 |
| マグネット式 | 手軽に着脱できる | スチール製の窓枠 |
これらの中でも、特に賃貸物件での使用を考えると、安定性と使い勝手の面からつっぱり式がベストな選択となるでしょう。取り付け後の安定性が高く、長期使用にも耐えられる構造になっているためです。
他のタイプと比べても、つっぱり式は確実な固定力があり、大きな窓にも対応できる 汎用性の高さが特徴です。お部屋の条件や用途に応じて、最適なタイプを選んでみてください。
賃貸でも取り付けられるつっぱり式ブラインドの選び方

賃貸物件でつっぱり式ブラインドを選ぶ際は、窓枠のサイズ測定から始めましょう。見た目の好みだけでなく、素材の特性や遮光性能、お部屋の使用環境に合わせた選択が大切です。
予算に応じて選べる価格帯も幅広く、取り付けやすさも製品によって異なるため、自分で設置できるか確認しておくことをおすすめします。特に窓枠との隙間や突っ張り棒の耐荷重は、設置後のトラブルを防ぐ重要なポイントになってきます。
窓枠のサイズ測り方
正確な寸法を測ることは、つっぱり式ブラインドを選ぶ際の最も重要なステップです。窓枠に合わないサイズを購入してしまうと、取り付けができなかったり、隙間から光が漏れたりする原因となります。
測り方のポイントは、窓枠の内側と外側の両方のサイズをしっかりと確認することです。まず、メジャーを使って窓枠内側の幅と高さを測りましょう。次に外側の寸法も同様に計測します。必ず3か所(上部・中央・下部)を測定して、最も小さい数値を採用してください。
つっぱり式ブラインドを設置する際に必要な測定箇所は以下の通りです。
- 窓枠内側の幅(左右)と高さ(上下)
- 窓枠外側の幅(左右)と高さ(上下)
- 窓枠の奥行き(壁からガラスまでの距離)
特に気を付けたいのが、窓枠の形状による制限です。斜めになっている窓枠や段差がある場合は、つっぱり式ブラインドが取り付けられない可能性があります。また、エアコンの室外機やベランダの手すりなど、窓の周囲に障害物がないかも確認しましょう。
測定値に余裕を持たせすぎると、ブラインドと窓枠の間に大きな隙間ができてしまいます。逆に小さすぎると取り付けができないため、製品の取り付け可能サイズの範囲内におさまるよう慎重に選んでください。カタログやオンラインショップの商品ページには、推奨サイズが記載されているのでそちらも参考にしましょう。
素材の違いと特徴
つっぱり式ブラインドの素材選びは、お部屋の雰囲気や使用環境によって大きく変わってきます。主要な素材にはそれぞれ特徴があり、用途に合わせて選ぶことが重要です。
代表的な素材として、アルミ製、樹脂製、木製の3種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
| 素材 | メリット | デメリット | 適した場所 |
|---|---|---|---|
| アルミ | 軽量、お手入れ簡単、価格が手頃 | 遮光性やや低め、金属音が気になる | リビング、寝室 |
| 樹脂 | 耐水性が高い、遮光性が良好、静音 | 重さがある、価格が比較的高め | 浴室、キッチン |
| 木製 | 高級感がある、断熱性が高い、静音 | 重さがある、湿気に弱い、高価格 | 和室、書斎 |
アルミ製は最も一般的で、軽量なため突っ張り式との相性が良好です。お手入れも簡単で、水回りでも使用できるのが特徴ですね。ただし、スラットとスラットが当たる際の金属音が気になることもあります。
樹脂製は水や湿気に強く、浴室やキッチンなどの水回りに最適です。遮光性も高いため、しっかりと光を遮りたい場所におすすめ。ただし、アルミと比べると重さがあるので、突っ張り棒の耐荷重をしっかり確認しましょう。
木製は高級感があり、お部屋のインテリアとして映えます。断熱性も高いため、夏の暑さ対策にも効果的。しかし、重量があり湿気にも弱いため、つっぱり式での使用には注意が必要です。
素材選びのポイントは、設置場所の環境と求める機能性のバランスを考えること。取り付け後のメンテナンス性も考慮に入れて、長く快適に使える素材を選んでみてください。
遮光・断熱性能の基準
つっぱり式ブラインドの遮光・断熱性能は、快適な室内環境を作る上で重要な要素です。製品選びの際は、自分の生活スタイルに合った性能レベルを選ぶことが大切になります。
遮光性能は1級から3級までの等級で表示されており、1級は遮光率99.99%以上と最も光を通しにくい仕様となっています。寝室や映画鑑賞を楽しむリビングには1級遮光がおすすめですよ。2級は遮光率99.80%以上、3級は99.40%以上で、書斎やダイニングなど、程よい明るさを保ちたい場所に適しています。
断熱性能については、スラット(羽根)の素材や構造によって大きく異なります。ハニカム構造を採用した製品は、空気層による優れた断熱効果を発揮します。一般的な平板タイプと比べて、約2倍の断熱効果が期待できるでしょう。
性能を判断する際のポイントは以下の通りです。
- 遮光等級(1級〜3級)の表示確認
- 断熱材の使用有無
- スラットの構造(中空か平板か)
- 製品の厚み(厚いほど断熱効果が高い)
特に夏場の西日対策や冬場の結露防止を考えている方は、断熱性能にこだわった製品を選びましょう。ただし、性能が高くなるほど重量も増えるため、つっぱり式の耐荷重との兼ね合いも考慮する必要があります。
近年は遮光と断熱の両方に優れたダブル機能タイプも増えてきました。価格は少し高めですが、1年を通して快適に過ごせる住環境を実現できますよ。お部屋の向きや気候条件に応じて、最適な性能の製品を選んでみてください。
価格帯の目安
つっぱり式ブラインドの価格は、サイズや素材、機能によって大きく変動します。一般的な製品の相場をお伝えしながら、予算の目安を具体的に見ていきましょう。
標準的なつっぱり式ブラインドは、幅90cm×高さ180cmのサイズで3,000円〜8,000円程度が中心的な価格帯となっています。最もリーズナブルなアルミ製の基本タイプなら5,000円前後で購入できるため、気軽に試してみることができます。
機能性を重視する場合は予算に余裕を持たせる必要があります。遮光性や断熱性を高めた製品は8,000円〜15,000円ほどで、木製タイプになると20,000円を超えることもあるでしょう。
| 素材・機能 | 価格帯(90×180cm) | 特徴 |
|---|---|---|
| アルミ基本タイプ | 3,000〜8,000円 | コスパ良好、軽量 |
| 樹脂製(遮光) | 8,000〜15,000円 | 高遮光、水回りOK |
| 木製(断熱) | 15,000〜25,000円 | 高級感、保温性高 |
取り付け費用が不要なため、通常のブラインドと比べるとトータルコストは抑えられます。ただし、大きなサイズになるほど価格は上がりやすく、幅200cm以上の製品では1.5〜2倍程度の価格になる点に注意が必要です。
初めて購入する方には、まずはリーズナブルなアルミ製から始めることをおすすめします。使用感を確かめてから、より機能性の高い製品にステップアップするという方法も賢い選択といえるでしょう。
つっぱり式ブラインドの取り付け方

つっぱり式ブラインドの取り付けは、工具不要で誰でも簡単に設置できるのが特徴です。基本的な手順は、付属の突っ張り棒を窓枠にセットして固定し、ブラインド本体を取り付けるだけなので、初めての方でも安心して作業できます。
ただし、つっぱり式ブラインドをしっかりと固定するには、窓枠との隙間を適切に調整することが大切です。取り付け前の採寸や準備をしっかり行い、設置後は定期的に固定具の緩みをチェックしましょう。準備から設置まで、順序立てて丁寧に行うことで、安全で快適なブラインドライフを楽しめるようになりますよ。
取り付け前の準備物
つっぱり式ブラインドを取り付ける前に、必要な道具と材料をすべて揃えておくことで、スムーズな設置作業が可能になります。基本的には製品に付属している部品だけで設置できますが、いくつかあると便利な道具もあります。
まずは製品に同梱されている部品を確認しましょう。つっぱり式ブラインドの基本セットには、ブラインド本体、固定具、取り付け説明書が含まれています。部品の不足がないか、必ず開封時にチェックしてください。
設置をスムーズに進めるために、以下の道具を用意しておくと作業がより簡単になります。
- メジャーまたは巻尺(窓枠の採寸用)
- 水平器(水平・垂直の確認用)
- 軍手(手を保護するため)
- 脚立や踏み台(高所作業用)
- 雑巾(設置後の拭き取り用)
特に水平器は、つっぱり式ブラインドを真っすぐに取り付けるためにとても重要なアイテムです。傾いて設置してしまうと、使用時にブラインドが片側に寄ってしまったり、スムーズに動かなくなったりする原因となります。
また、天井が高い場所に設置する場合は、安全のため必ず脚立や踏み台を使用しましょう。椅子やテーブルの上に乗って作業するのは大変危険です。
部品や道具を確認したら、作業スペースの確保も忘れずに。窓の前に家具や小物がある場合は、あらかじめ移動させておくことをおすすめします。余裕を持って作業できる環境を整えることで、安全かつ正確な取り付けが可能になりますよ。
設置手順と注意点
つっぱり式ブラインドの設置は、正しい手順で行うことで安定した取り付けが可能です。作業の流れに沿って、具体的な設置方法をご説明します。
基本的な設置手順は、窓枠の採寸から始まり、上部固定具の取り付け → ブラインド本体の設置という流れで進めていきます。特に重要なのは、最初の位置決めと水平確認です。
まずは上部固定具を窓枠上部にセットします。この時、左右の位置を正確に測り、中心を合わせることがポイントです。固定具は窓枠にしっかりと密着させ、がたつきがないことを確認しましょう。
ブラインド本体を取り付ける際は、2人で作業すると安全です。本体を上部固定具に差し込んでから、下部固定具をスライドさせて固定します。この時、突っ張り棒の締め付けは強すぎず、弱すぎず、適度な力加減で行いましょう。
設置後は必ず動作確認を行います。ブラインドをゆっくり上下させて、スムーズに動くか確認します。また、固定具と窓枠の間に隙間がないか、本体が傾いていないかもチェックしてください。
注意点として、以下の3つを意識しながら作業を進めることをおすすめします。
- 上部の固定具は必ず水平を保つ
- 突っ張り棒の締め付けは段階的に調整する
- 取り付け後24時間は強い操作を避ける
トラブルを防ぐために、説明書をよく読み、順序立てて丁寧に作業を進めることが大切です。正しい手順で設置することで、長く快適にお使いいただけるはずです。
トラブル対処法
つっぱり式ブラインドの設置後に発生しやすいトラブルには、適切な対処方法があります。早めの対応で快適な使用環境を維持できるので、主な症状と解決策を押さえておきましょう。
最も多いトラブルは、使用していくうちに発生する固定具の緩みです。これは突っ張り棒の圧力が徐々に弱くなることで起こります。定期的に固定具の締め付けを確認し、緩みを感じたらすぐに締め直しましょう。
ブラインドが斜めになってしまう場合は、上下の固定具の位置がずれている可能性があります。一度取り外して、水平器を使って左右のバランスを確認しながら付け直してみてください。
スラットの開閉がスムーズでない時は、操作紐の絡まりが原因かもしれません。紐を丁寧にほぐし、からまりを解消することで改善されます。それでも動きが悪い場合は、固定具の位置を微調整してみましょう。
突っ張り棒の跡が窓枠に付いてしまった時は、中性洗剤で優しく拭き取ります。跡が残りやすい素材の窓枠には、あらかじめ保護シートを貼っておくと安心です。
がたつきや異音が気になる場合は、各部品の接続部分を確認します。緩みがある箇所は締め直し、必要に応じて付属のスペーサーなどで調整するとよいでしょう。
万が一、商品が破損した場合は無理な修理は避け、メーカーのサポートセンターに相談することをおすすめします。保証期間内であれば、交換や修理に対応してもらえる可能性があります。
これらのトラブルの多くは、定期的なメンテナンスで予防できます。月1回程度の点検を習慣にすることで、長く快適にお使いいただけるはずです。
つっぱり式ブラインドのお手入れ方法

長く快適につっぱり式ブラインドを使うためには、適切なお手入れが欠かせません。日常的なホコリ取りから定期的な清掃まで、メンテナンス方法をマスターすることで美しさを保つことができます。
汚れやすい場所なので、放っておくとカビの原因にもなってしまいます。特に結露が気になる時期は、しっかりと換気を行いながら適切なお手入れを心がけましょう。つっぱり式ブラインドの素材に合わせた掃除方法を知っておくと、より長持ちさせることができますよ。
日常的なメンテナンス方法
つっぱり式ブラインドを長く美しく使い続けるためには、毎日の簡単なお手入れが大切です。基本的な清掃方法を身につければ、面倒な大掃除の手間も減らすことができます。
普段のお手入れは、柔らかい布やハンドモップでブラインドのスラット(羽根)を優しく払うことから始めましょう。上から下へ、1枚1枚丁寧にホコリを落としていきます。この時、強い力でこすらないことがポイントですよ。
週1回程度は、スラットを閉じた状態で両面からホコリを取り除いてあげましょう。ハンディタイプの掃除機を使う場合は、ノズルにブラシを付けて弱めの吸引力で掃除すると安全です。
特に気をつけたいのが突っ張り部分の清掃です。固定具の周りにホコリが溜まると、緩みの原因になることも。固定部分は月1回程度、念入りにチェックしながら掃除してみましょう。
キッチンやリビングなど汚れが付きやすい場所に設置している場合は、3か月に1度くらいの頻度で、薄めた中性洗剤で丁寧に拭き掃除するのがおすすめです。ただし、洗剤を使用する際は必ず固く絞った布で拭き、最後は乾いた布でしっかり水分を拭き取りましょう。
また、つっぱり式ブラインドの耐久性を保つために、スラットの開閉は優しく行うことを心がけてください。乱暴な操作は本体の歪みや故障の原因となってしまいます。
こまめなお手入れを習慣にすることで、つっぱり式ブラインドの美しさと機能性を長く保つことができますよ。毎日ほんの少しの時間でも、できる範囲でのメンテナンスを続けていきましょう。
汚れ・カビ対策
つっぱり式ブラインドの清潔さを保つには、適切な汚れ・カビ対策が重要です。特に水回りや結露の多い窓に設置している場合は、念入りなケアが必要になってきます。
汚れやカビが発生した場合は、できるだけ早めの対処がポイントです。放置してしまうと、取れにくい汚れになったり、カビが広がったりしてしまいます。素材に合わせた適切な洗剤を選ぶことが、効果的な清掃の秘訣になりますよ。
頑固な汚れには、中性洗剤を薄めた溶液を使用しましょう。スラットを1枚ずつ丁寧に拭き、その後しっかりと水拭きをして洗剤を残さないようにします。特に油汚れが気になるキッチン周りでは、重曹水での拭き掃除も効果的です。
カビ予防の基本は、換気と水分管理です。結露が発生しやすい時期は、1日2回以上の換気を心がけましょう。また、窓周りの通気性を確保するため、ブラインドと窓の間に適度な空間を設けることをおすすめします。
もしカビが発生してしまった場合は、以下の手順で対処します。
- カビ取り剤をスプレーし、10分ほど放置
- 柔らかい布で優しく拭き取る
- きれいな布で水拭きを繰り返す
- 最後に乾いた布でしっかり水分を拭き取る
お手入れ後は、つっぱり式ブラインドの固定具が緩んでいないか確認することも大切です。水拭き後の緩みは、転倒事故の原因となる可能性があるので注意が必要ですよ。
定期的なメンテナンスを行うことで、清潔で快適なブラインドライフを楽しむことができます。汚れやカビの予防から、素早い対処まで、しっかりと管理していきましょう。
よくある質問

つっぱり式ブラインドの使用にあたって、お客様からよくいただく質問をまとめてご紹介いたします。取り付けの際の疑問点や、使用中のトラブル対処法まで、実際の声に基づいた内容を解説していきましょう。
特に多いご質問は、設置時の強度や長期使用での不具合に関するものです。安全に使用していただくために、製品に合った正しい設置方法と日々のメンテナンスが大切になってきます。これらの疑問や悩みについて、具体的な解決方法を項目ごとにご説明いたしますね。
取り付けに関する疑問
つっぱり式ブラインドの取り付けに関して、よくある疑問とその回答をご説明します。
設置時に最も心配なのは、つっぱり式ブラインドが本当に安全に固定できるのかという点です。正しい手順で取り付ければ、通常のブラインドと変わらない安定性を確保できます。突っ張り棒の耐荷重を確認し、窓枠にしっかりと固定することがポイントになってきます。
次によく寄せられる質問が、窓枠の素材による取り付け制限についてです。木製やアルミ製など、ほとんどの一般的な窓枠に対応していますが、特殊な形状や古い窓枠の場合は事前に確認が必要です。取り付け面の強度や平滑性をチェックしてみましょう。
また、賃貸物件特有の質問として、退去時の原状回復についても気になる方が多いようです。つっぱり式ブラインドは壁に穴を開けないため、基本的に跡が残りません。ただし、長期間の使用で窓枠に跡が付くことがあるため、定期的に位置を微調整することをおすすめします。
取り付け時の失敗を防ぐために、まずは説明書をしっかり読むことが大切です。分からない点があれば、メーカーのサポートに問い合わせることで、安全な取り付けが可能になります。
このように、つっぱり式ブラインドは適切な知識があれば、誰でも安全に設置できる便利なアイテムといえるでしょう。ただし、突っ張り棒の定期的な締め直しなど、継続的なメンテナンスは忘れずに行いましょう。
使用時の注意点
つっぱり式ブラインドを快適に使用するための重要なポイントをご説明します。
日常的な使用において最も注意すべきは、開閉時の操作方法です。急な開閉や強い力での操作は、本体の歪みや破損の原因となります。スラットは必ずゆっくりと丁寧に動かすようにしましょう。
突っ張り棒の緩みは定期的にチェックが必要です。特に季節の変わり目は、温度変化による伸縮で固定力が変わることがあるため、月1回程度は固定具の状態を確認してみてください。
カーテンと違って耐風性に優れていますが、窓を開けたまま放置するのは避けましょう。強風時にスラットが激しく揺れると、突っ張り棒が外れる可能性があります。
また、結露対策も大切なポイントです。冬場は特に窓際の結露が気になりますが、水滴がブラインドに付着すると錆びやカビの原因に。朝晩の換気をしっかり行い、結露が発生したら早めに拭き取ることをおすすめします。
お子様やペットのいるご家庭では、スラットで遊ばないよう注意が必要です。特にコードやチェーンには絡まる危険があるため、巻き取り器具を使用して高い位置で固定しておきましょう。
長期間留守にする際は、完全に閉めきらず、少し隙間を開けた状態にしておくと安心です。これにより室内の温度変化を緩和し、突っ張り棒への負担を軽減できますよ。
使用環境に合わせた適切な管理を心がけることで、つっぱり式ブラインドを長く快適に使い続けることができます。定期的なメンテナンスと合わせて、これらの注意点を意識した使い方を心がけていきましょう。
故障・破損時の対応
つっぱり式ブラインドの故障や破損時の対応について、具体的にご説明します。
万が一の故障や破損に備えて、対処法を知っておくことは大切です。早めの対応で大きなトラブルを防ぐことができますので、異常を感じたらすぐに確認しましょう。
まず、よくある故障のケースとして、スラットの動きが悪くなる、引っかかる、片寄りが発生するなどがあります。この場合、まずは固定具の緩みや歪みをチェックしてください。緩んでいる場合は、突っ張り棒を適度な強さで締め直すことで改善する可能性があります。
スラットが破損してしまった場合は、素材や破損状態によって対応が異なります。小さな破損であれば、専用の補修キットで直せることもありますが、大きな損傷の場合は部品交換や本体の買い替えを検討する必要があるでしょう。
突っ張り棒が折れたり、固定具が破損したりした場合は、すぐに使用を中止してください。これらの部品は製品の安全性に直結するため、メーカーに問い合わせて純正の交換部品を入手することをおすすめします。
製品保証期間内であれば、メーカーでの修理や交換が可能な場合もあります。購入時の保証書は大切に保管し、故障時にはすぐに確認できるようにしておきましょう。
長期使用による劣化で修理が難しい場合は、新しい製品への交換を検討します。その際は、前回の経験を活かして、より使用環境に適した製品を選ぶことが賢明です。
このように、つっぱり式ブラインドのトラブルには、適切な対処方法があります。日頃からの点検と早めの対応を心がけることで、快適な使用を継続できますよ。
まとめ

つっぱり式ブラインドについて、選び方から取り付け方、お手入れまで幅広く見てきましたね。賃貸物件でも安心して使える便利なアイテムだとわかりました。
つっぱり式ブラインドの最大の魅力は、壁に穴を開けずに設置できる点です。賃貸物件での退去時の修繕費用を気にせず、手軽に窓周りの目隠し対策ができます。
選び方のポイントは、まず窓枠のサイズを正確に測ることから始めましょう。素材は、アルミ製やウッド調など、お部屋の雰囲気に合わせて選んでみてください。遮光や断熱性能も重要な選択基準になります。
取り付けは慎重に行うことが大切です。必要な工具を揃え、説明書の手順に沿って丁寧に設置していきましょう。取り付け後のガタつきやゆがみは、早めに調整することをおすすめします。
日々のお手入れも忘れずに。定期的な掃除で、つっぱり式ブラインドを長く美しく保つことができますよ。
これから窓周りの目隠し対策を考えている方は、ぜひつっぱり式ブラインドを候補の1つに加えてみてはいかがでしょうか。この記事で学んだ知識を活かして、お部屋に合った素敵なつっぱり式ブラインドを見つけていただければと思います。