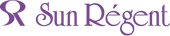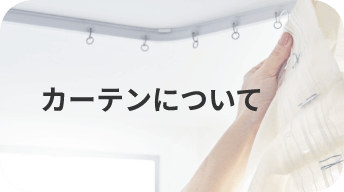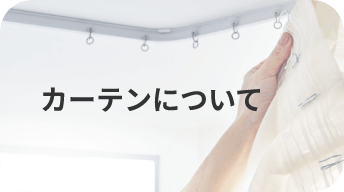Contents
カーテンの裾が床に引きずって擦り切れてしまった経験はありませんか?また、お子様が遊んでいて引っ掛けてしまったり、掃除機で吸い込んでしまったりして破れてしまうこともよくあることです。
「カーテンが破れてしまったけど、新品を買い替えるのはもったいない」「裾上げの直し方がわからず、床に引きずったままになっている」といった声をよく耳にします。
カーテンの直しは、破れの程度や修理の難しさによって、自分で直すか専門業者に依頼するかを選択することが大切です。小さな破れや裾上げなら、実は自分でも簡単に直せることが多いのです。
この記事では、カーテンの直し方について、自分でできる修理の方法から専門業者への依頼まで、具体的な手順とポイントを詳しく解説していきます。カーテンの修理費用を抑えながら、快適な住環境を保つために必要な情報をわかりやすくお伝えしていきましょう。
カーテンの修理方法とは

カーテンの修理には、自分で直せる簡単な補修から専門業者に依頼すべき大掛かりな修理までいろいろな種類があります。破れやほつれ、裾上げなど、症状に合わせて適切な修理方法を選ぶことがポイントでしょう。
自分で修理する場合は、まず破れの大きさや場所、生地の状態をよく確認してみましょう。小さな穴や裾のほつれは、縫い物の基本的な知識があれば家庭でも直せることが多いですよ。一方で、大きな破れや生地の劣化が進んでいる場合は、プロの技術が必要になってきます。
自分で修理できる破れや不具合の種類
カーテンの修理で自分でも直せる不具合には、いくつかの代表的なパターンがあります。まずは症状を把握して、適切な対処方法を見極めることが大切です。
小さな破れやほつれは、手軽に自分で修理できる代表的な症状です。特に裾や端の部分の5センチメートル未満の破れなら、針と糸があれば簡単に直すことができます。また、アジャスターフックの調整だけで直せる裾上げも、初心者でも安心して取り組める修理といえるでしょう。
具体的に自分で修理可能な不具合をご紹介しましょう。
- 裾のほつれ(5センチメートル未満)
- フックが外れた箇所の修復
- 小さな引っかき傷の補修
- プリーツの歪み調整
- アジャスターフックでの長さ調整
一方で、生地が大きく裂けている場合や、劣化による複数箇所の破れがある場合は、自分での修理は避けたほうが無難です。また、厚手の遮光カーテンや特殊な加工が施されているカーテンの修理は、専門的な技術や道具が必要になってくるため、業者への依頼をおすすめします。
カーテンの生地の状態をよく観察し、破れの大きさや場所を確認することで、自分で直せるかどうかの判断ができます。迷った場合は、まずは写真を撮って専門店に相談してみるのもよいでしょう。自己判断で無理に修理を試みて、かえって状態を悪化させてしまうことは避けたいものですね。
修理の難易度と道具の準備
カーテンの修理は難易度によって3段階に分けることができます。初心者でも安心して取り組める「簡単」な修理から、経験者向けの「中級」、そして専門的な技術が必要な「上級」まで、それぞれの目安を把握しておくと便利です。
基本的な裾上げやフックの付け替えなどの簡単な修理なら、縫い物の経験がなくても気軽にチャレンジできますよ。必要な道具も家庭にあるものがほとんどなので、手軽に始められます。
修理に必要な基本的な道具は以下のとおりです。
- 裁縫セット(針、糸、はさみ、メジャー)
- アイロンと霧吹き
- 補修用の布や裾上げテープ
中級レベルの修理には、5センチメートル程度までの破れの縫い合わせや、ほつれの始末などが含まれます。この場合は直線縫いや返し縫いなどの基本的な縫製技術が必要になってきます。
上級レベルになると、大きな破れの修復や生地の張り替えなど、専門的な技術と特殊な道具が必要になります。このような修理は、むしろ専門業者に依頼することをおすすめしますね。
修理を始める前に、カーテンの生地の特性も確認しておきましょう。遮光カーテンや防炎カーテンは特殊な加工が施されているため、一般的な裁縫道具では対応が難しい場合があります。また、薄手のレースカーテンは繊細な扱いが必要で、力加減を誤ると破れが広がってしまうこともあるので注意が必要です。
道具の準備では、カーテンの色に合った糸を選ぶことも大切なポイントです。また、補修用の布を使う場合は、なるべくカーテンと同じ素材や色味のものを選びましょう。事前に小さな端切れで試し縫いをしてみると、仕上がりのイメージがつかみやすいですよ。
業者に依頼すべき症状の見分け方
カーテンの修理を自分で行うか専門業者に依頼するか、その判断基準をはっきりさせることが重要です。以下のような症状が見られる場合は、専門業者への依頼を強くおすすめします。
生地全体の劣化が進んでいる場合は、一箇所を直しても他の部分がすぐに破れてしまう可能性が高いです。特に日光や熱で生地が脆くなっているときは、素人の修理では返って状態が悪化してしまうかもしれません。
大きな破れや複数箇所の損傷がある場合も、専門家の技術が必要になってきます。目安として10センチメートル以上の破れや、3箇所以上の破損箇所がある場合は業者に任せましょう。
特殊な加工が施されているカーテンの修理も要注意です。遮光カーテンや防炎カーテンは、一般的な裁縫道具や手法では対応が難しく、機能性を損なう可能性があります。
また、以下のような症状も専門業者に相談すべきケースといえるでしょう。
- 生地の継ぎ目からの大きな裂け
- カーテンレールに近い上部の破損
- 特殊な縫製や装飾が施された部分の破れ
- 厚手の生地の裂け目や破損
修理費用が気になる方もいらっしゃるでしょうが、素人の修理で取り返しのつかない状態になってしまうリスクを考えると、迷った時点で専門家に相談するのが賢明です。
プロの技術を必要とするかどうか判断に迷う場合は、まずはカーテンの状態を写真に撮って、専門店に相談してみることをおすすめします。多くの業者が無料で相談に応じてくれますよ。

カーテンの裾上げ修理の手順

カーテンの裾上げは家庭でも手軽にできるお直しの代表格です。アジャスターフックでの簡単調整から、裾上げテープを使った方法、手縫いでの修繕まで、状況に応じた方法を選べます。
裾上げ修理は、カーテンの長さを調整して床との摩擦を防ぎ、擦り切れや汚れを予防する大切なメンテナンスです。床から1〜2センチ程度の隙間を目安に長さを決めると、見た目も美しく使い勝手の良い仕上がりになりますよ。それぞれの修理方法について、道具の準備から手順まで詳しく見ていきましょう。
アジャスターフックでの簡単調整
カーテンの裾上げで最も手軽な方法が、アジャスターフックを使った調整です。特別な道具や技術がなくても、誰でも簡単に長さを変えられます。
アジャスターフックとは、フックの部分が伸縮できる便利なカーテンパーツのことです。多くのレディメイドカーテンに標準で付属している小さなプラスチック製の金具で、長さを数段階に調整できる仕組みになっています。
アジャスターフックでの調整手順は非常にシンプルです。まずカーテンを取り付けたままの状態で、床からの理想的な長さを確認しましょう。次に、上部のフックを持ちながら下部を引っ張ると、カチッという音とともに長さが変わっていきます。
具体的な調整のコツをご紹介します。
- フックは左右対称に同じ長さに調整する
- 一度に大きく変えずに少しずつ調整する
- 調整後はしっかりとロックされているか確認する
裾上げの理想的な長さは床から1〜2センチが目安です。長すぎると床との摩擦で傷みやすく、短すぎると見た目が悪くなってしまいます。
もしアジャスターフックでの調整以上に長さを変えたい場合は、裾上げテープや手縫いなど他の方法を検討してみてください。また、古いカーテンでアジャスターフックが壊れている場合は、ホームセンターなどで交換用パーツを購入できますよ。
この方法の最大のメリットは、カーテンを外さずに簡単に調整できることです。引っ越しや模様替えの際にも便利ですし、季節によって長さを微調整したい時にもおすすめの方法といえるでしょう。
裾上げテープを使った補修方法
裾上げテープを使うと、ミシンや手縫いの技術がなくても、カーテンの長さをしっかりと調整できます。
裾上げテープは両面テープのような接着力を持つアイロン接着テープで、熱を加えることで布地同士をしっかりと固定できる便利なアイテムです。アイロンさえあれば初心者でも簡単に使えるため、カーテンの裾上げ修理におすすめの方法といえます。
使用する道具は、裾上げテープ、はさみ、アイロン、ものさし、そしてカーテンを平らに置くためのシーツなどです。まずカーテンを平らに広げ、床から1〜2センチ上がるように折り目をつけていきましょう。このとき、まっすぐな仕上がりにするために、ものさしで丁寧に測ることがポイントです。
具体的な手順は次のようになります。
- カーテンを裏返しにして折り目をつける
- 折り目に沿って裾上げテープを配置する
- アイロンをあて、30秒ほど押さえて接着する
- 余分なテープをはさみでカットする
特に気をつけたいのは、アイロンの温度設定です。カーテンの素材に合わせて適切な温度を選ばないと、生地が焦げたり溶けたりする可能性があります。取扱い表示を確認し、まずは目立たない端で試し付けをしてみることをおすすめしますよ。
裾上げテープは洗濯にも強く、長期間の使用に耐えられます。ただし、厚手の遮光カーテンなど重い生地の場合は、テープだけでなく簡単な縫い目を加えると、より安心して使用できるでしょう。また、カーテンの生地によっては接着が弱くなることもあるので、購入時に適切なテープを選ぶことも大切です。
手縫いでの直し方のコツ
カーテンを手縫いで直す方法は、少し手間はかかりますが、きれいな仕上がりが期待できる方法です。裁縫が得意な方はもちろん、基本的な縫い方さえ覚えれば初心者でも挑戦できますよ。
手縫いでカーテンを直すときは、まず丈夫な糸を選ぶことが重要です。カーテンは重い生地なので、普通の裁縫糸では切れやすくなってしまいます。カーテン専用の丈夫な糸や二重に通した糸を使うと安心です。
裾上げをする場合は、まず床から適度な長さを測って折り目をつけていきましょう。折り目をまっすぐにするために、アイロンで軽く押さえておくと作業がしやすくなります。縫い方は、2センチ程度の間隔で返し縫いをするのがおすすめです。
基本的な手順を詳しく説明すると、以下のようになります。
- 折り目に沿って待ち針を打つ
- 返し縫いで端から丁寧に縫っていく
- 10センチメートルごとに糸を固定する
- 最後は糸をしっかり結んで始末する
縫い目は裏側からでも目立たないように、できるだけ小さな針目で縫うことがコツです。また、カーテンの重みで糸が切れないように、縫い始めと縫い終わりはしっかりと返し縫いをして補強しておきましょう。
手縫いならではの利点は、カーテンの生地に合わせて細かい調整ができることです。厚手の生地なら強めに、薄手の生地なら優しく縫うなど、素材に応じた縫い方を選べます。また、途中で長さを微調整することもできるので、より正確な仕上がりが期待できますよ。
カーテンを外して作業する場合は、広いスペースで平らに広げて作業すると、折り目がまっすぐになりやすいでしょう。手縫いは時間がかかりますが、丁寧に仕上げることで長持ちする修理になります。
カーテンの破れ修理のやり方

カーテンの破れは補修方法によって、見栄えの良い仕上がりにすることができます。小さな穴やほつれの場合は専用の補修キットを使うと手軽に直せますし、大きめの破れでも裏側から同系色の布を当てて縫い合わせることで目立たなくできるでしょう。
破れの状態や生地の素材によって最適な修理方法は異なってきます。カーテンの破れが生地の端や縫い目に近い場合は手縫いでの修繕がおすすめですが、真ん中付近の破れは補修テープや市販のリペアキットを活用すると良いでしょう。それぞれの特徴を理解して、状況に合った修理方法を選んでみましょう。
小さな穴や破れの補修手順
小さな穴や破れの補修には、適切な修理方法を選ぶことで見栄え良く直すことができます。生地の状態や破れの場所によって最適な方法が変わってきますよ。
基本的な補修手順は以下の通りです。
- 破れた箇所の周辺をアイロンでしわを伸ばす
- 裏側から補修用の布を当てて仮止めする
- 表側から破れに沿って細かく縫い合わせる
- アイロンで仕上げて補修箇所を馴染ませる
まず初めに、補修箇所の汚れを落として生地を清潔な状態にしましょう。その後、アイロンでしわを伸ばすことで、より綺麗な仕上がりが期待できます。
穴の大きさが2センチ未満の場合は、カーテンの裏側から同系色の薄手の布を当てて固定するのがおすすめ。布は破れより1センチ程度大きめにカットして使うと安定感が増しますよ。
補修布を仮止めしたら、表側から破れの形に沿って細かく縫い合わせていきます。縫い目が目立ちすぎないよう、カーテンと同じ色の糸を使うのがポイントです。
最後にもう一度アイロンをかけると、補修箇所が周囲に馴染んできれいに仕上がります。特に化繊素材の場合は、アイロンの温度に注意して低めの設定で押さえましょう。
穴が小さければ小さいほど目立たない仕上がりになるので、破れに気付いたらすぐに対処することをおすすめします。放置すると穴が大きくなってしまい、修理が難しくなる可能性がありますよ。
ほつれの直し方と予防法
カーテンのほつれは放置すると徐々に広がってしまう厄介な症状です。早めの対処で美しい状態を保ち、カーテンを長持ちさせることができます。
ほつれの直し方は、症状によって使い分けるのがポイントでしょう。裾や端のほつれは、まずほつれている糸を切り揃えてから、同じ色の糸で縫い留めていきます。糸はカーテンの色に近いものを選ぶと目立ちにくくなりますよ。
特に裾のほつれは、床との摩擦で広がりやすい傾向にあります。ミシンを使える方なら、三つ折り縫いで補強するのがおすすめ。手縫いの場合は、まつり縫いで丁寧に縫い留めていきましょう。
中央部分のほつれには、市販の補修テープを活用すると便利です。アイロンで貼り付けるタイプなら、縫う手間もなく簡単に直せます。ただし、生地の素材に合った温度設定を守ることが大切ですよ。
ほつれを予防するためには、日頃のお手入れが重要です。定期的に以下のようなケアを心がけましょう。
- カーテンの開閉は優しく行う
- 掃除機をかける時は吸い込まないよう注意
- 洗濯時はネットを使用する
- 床との接触を避けるため適切な長さに調整
また、カーテンレールの状態も要チェックポイント。レールに傷や歪みがあると、開閉時に生地を傷めやすくなります。レールの清掃やメンテナンスも忘れずに行いましょう。
ほつれの予防には、カーテンの取り付け位置も大切な要素です。床から1〜2センチ程度の隙間があれば、擦れによるほつれを防ぐことができます。裾上げの調整は、アジャスターフックを使えば簡単にできますよ。
補修用の市販キットの使い方
カーテンの破れを手軽に修理できる市販のキットが、最近では多く販売されています。これらのキットを使えば、縫い物が苦手な方でも簡単にカーテンを直すことができます。
市販の補修キットには、主にアイロン接着タイプとテープタイプの2種類があります。アイロン接着タイプは熱で貼り付けるため、しっかりと固定できる特徴があります。一方のテープタイプは手軽に使える反面、耐久性はやや劣ります。
キットを使う際は、まず破れの周辺をきれいに整えることが大切です。ほつれた糸は丁寧にカットし、アイロンでしわを伸ばしておきましょう。その後、キットの説明書に従って補修を進めていきます。
補修キットを選ぶ際は、カーテンの素材や色に合ったものを選ぶことが重要です。遮光カーテンやレースカーテンなど、生地の特性によって適切なキットが異なってきます。また、補修箇所が目立たないよう、なるべくカーテンに近い色味のものを選びましょう。
使用時の注意点として、アイロンの温度設定には特に気を付ける必要があります。生地が溶けてしまわないよう、まずは端で試し付けをしてみることをおすすめします。また、破れが大きい場合は、キットだけでなく手縫いを組み合わせるとより丈夫な仕上がりになりますよ。
補修キットは手軽で便利ですが、あくまでも応急処置的な性質があります。頻繁に洗濯するカーテンや、大きな破れがある場合は、専門業者による修理を検討してみてください。
プロに修理を依頼する場合

破れや裾上げの状態によっては、自分で直すのが難しい場合もあります。カーテンの生地が高価なものだったり、大きな破れや複雑な修理が必要なケースでは、むしろプロに任せたほうが安全で確実です。
カーテンの修理専門店や、クリーニング店など、様々な業者が修理サービスを提供しています。修理方法や料金、作業期間は業者によって異なりますので、複数の店舗に見積もりを依頼して比較検討してみましょう。
修理料金の相場と期間
プロのカーテン修理にかかる費用は、修理内容や生地の種類によって大きく異なります。一般的な裾上げの場合、1枚あたり2,000円から5,000円程度が相場となっています。
小さな破れの修理では3,000円から8,000円ほどかかりますが、破れの大きさや場所によって料金は変動するでしょう。高級な生地や特殊な素材の場合は、さらに費用が上乗せされることもありますので注意が必要です。
具体的な料金の目安をご紹介します。
| 修理内容 | 料金相場 | 所要期間 |
|---|---|---|
| 裾上げ | 2,000〜5,000円 | 3〜7日 |
| 小さな破れ修理 | 3,000〜8,000円 | 5〜10日 |
| フック修理 | 1,500〜3,000円 | 2〜5日 |
| 大きな破れ修理 | 8,000〜15,000円 | 7〜14日 |
修理にかかる期間は、基本的に1週間前後が目安となっています。ただし繁忙期や修理内容によっては2週間以上かかる場合もあるので、余裕を持って依頼することをおすすめします。
また、出張費や見積もり料金が別途必要になる場合があるため、事前に料金体系をしっかり確認しましょう。クリーニングと修理をセットで依頼すると割引が適用される店舗もありますよ。
急ぎの修理にも対応できる業者もありますが、通常料金の1.5〜2倍程度の追加料金がかかることが一般的です。費用を抑えたい場合は、標準的な修理期間での依頼がおすすめですね。
業者選びのポイント
カーテンの修理業者を選ぶ際は、信頼性と技術力が重要なポイントとなります。適切な業者選びで、大切なカーテンを安心して任せられる修理パートナーを見つけることができます。
まず、実績と経験が豊富な業者を探しましょう。カーテン専門店や、カーテン修理の取り扱い実績が10年以上ある店舗を選ぶと安心です。修理サンプルや過去の施工例を見せてもらえる業者なら、仕上がりのイメージも掴みやすいでしょう。
お見積もりの明確さも重要な判断基準となります。修理費用の内訳や作業期間が詳しく説明されている業者は、トラブル防止の観点からも信頼できます。追加料金の有無や保証内容についても、事前にしっかり確認しておきましょう。
良い業者を見分けるポイントをご紹介します。
- 丁寧なカウンセリングと現物確認を行ってくれる
- 修理方法の選択肢を複数提案してくれる
- 料金体系が明確で見積もりが分かりやすい
- アフターフォローや保証制度が充実している
- 口コミやレビューの評価が高い
また、緊急時の対応力や臨機応変な相談対応ができるかどうかも重要です。カーテンの破れは予期せぬタイミングで起こることも多いため、急な依頼にも柔軟に対応してくれる業者を選びたいものです。
地域密着型の業者なら、出張修理や持ち込み修理など、お客様の都合に合わせたサービス提供が期待できます。大手チェーン店では対応できない細かなニーズにも応えてくれる可能性が高いでしょう。
相見積もりを取ることも賢明な選択です。同じ修理内容でも業者によって料金に差があるため、3社程度の見積もりを比較することで、適正価格での修理依頼が可能になります。
持ち込み修理と出張修理の違い

カーテンの修理方法には、自宅に持ち込む方法と業者に来てもらう出張修理の2つがあります。それぞれに特徴があるので、状況に応じて適切な方法を選びましょう。
持ち込み修理は、カーテンを外して店舗まで持参する方法です。出張費がかからない分、料金を抑えられるのが大きなメリット。また、店舗の設備を使った丁寧な修理が期待できます。ただし、大きなカーテンの場合は運搬が大変なので注意が必要ですよ。
一方の出張修理は、業者がご自宅まで来てその場で修理を行います。カーテンの取り外しや運搬の手間がなく、その日のうちに完了することも。特に重たい遮光カーテンや、複数枚まとめての修理の場合は便利な選択肢となるでしょう。
料金面では以下のような違いがあります。
| 修理方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 持ち込み | 基本料金が安い、丁寧な修理が可能 | 運搬が必要、時間がかかる |
| 出張 | その場で完了、手間がかからない | 出張費が必要、設備に制限あり |
選び方のポイントは、カーテンの大きさや枚数、修理の内容、予算などを総合的に考慮すること。たとえば小さな破れの修理なら持ち込みがお得ですが、大掛かりな修理は出張サービスを利用するのが賢明かもしれません。
カーテンを長持ちさせるコツ

カーテンを長く使い続けるためには、普段のお手入れと定期的なメンテナンスが欠かせません。適切な取り扱いと予防策を知っておくことで、突然の破れや不具合を防ぐことができるでしょう。
毎日の開け閉めで負担がかかるカーテンは、生地の特性を理解して丁寧に扱うことが大切です。定期的な掃除やほつれの早期発見、正しい開閉方法を心がけることで、カーテンの寿命を大幅に延ばすことができますよ。そして、日光による色あせや生地の劣化を防ぐための工夫も忘れずに取り入れてみましょう。
日々のお手入れ方法
カーテンを長持ちさせるためには日々の適切なお手入れが欠かせません。正しいケア方法を知って実践することで、カーテンの寿命を大幅に延ばすことができます。
まず基本的なお手入れとして、週1回程度の掃除が重要です。掃除機のブラシ付きノズルを使って、カーテンの表面についたホコリを優しく除去していきましょう。その際、強い力でこすらないよう注意が必要です。
洗濯の際は洗濯表示をよく確認し、手洗いが推奨される素材は必ず手洗いで。洗濯機を使う場合も、必ずネットに入れて優しく洗うことがポイントです。
また、カーテンの開閉時は両手でゆっくりと行い、片寄せカーテンの場合は必ず中央部分を持って動かすようにしましょう。レールに無理な力をかけると、カーテンの上部に負担がかかって破れの原因になります。
日光による色あせ防止には、2重カーテンやレースカーテンの活用がおすすめ。特に南向きの窓は紫外線が強いため、昼間はレースカーテンを閉めておくと良いでしょう。
お手入れの最後に、カーテンの生地全体をチェックして、小さなほつれや破れを見つけたら早めに対処することが大切です。こまめな点検と適切なケアを心がけることで、カーテンは何年も美しく保つことができますよ。
破れやすい箇所の予防策
カーテンの破れやすい箇所を知って予防することは、修理の手間やコストを抑える上で非常に重要です。普段から注意すべきポイントを押さえて、カーテンを長持ちさせましょう。
まず、最も破れやすい部分は開閉時に力がかかる上部です。特にフックを取り付ける箇所は負担が集中しやすいため、開閉は必ず両手でゆっくりと行うことが大切です。片手での乱暴な開け閉めは破れの原因となってしまいます。
次に注意したいのが床との接触部分です。カーテンの裾が床に引きずると摩擦で生地が傷みやすくなります。カーテンの長さは床から1〜2センチ程度の隙間を空けることで、擦り切れを防ぐことができますよ。
また、窓枠やドアノブなどの突起物にも要注意です。以下のような対策を講じることで、引っかかりによる破れを予防できます。
- 窓の周りの突起物にクッションテープを貼る
- カーテンストッパーを取り付けて揺れを抑える
- 家具との接触を避けるようレイアウトを工夫する
子供やペットがいるご家庭では、カーテンで遊ばないようにルールを決めることも大切なポイントです。特に下部は引っ張られやすいので、破れ防止のためにも注意が必要でしょう。
掃除機での清掃時も破れの原因となりやすいため、ノズルは優しく当てるようにします。また、洗濯の際は必ずネットに入れ、脱水は短めにすることで生地への負担を軽減できます。
これらの予防策を日頃から意識することで、カーテンの寿命を大幅に延ばすことができます。小さな心がけの積み重ねが、快適な暮らしを支える大切なポイントとなりますよ。
まとめ

カーテンの修理や直しについて、自分でできる範囲から専門家に依頼すべき場合まで、幅広く見てきました。
小さな破れや裾上げなど、簡単な修理であれば自分で対応できることがわかりましたね。アジャスターフックを使った裾上げや、補修キットを使った破れの修理など、特別な技術がなくても手軽にできる方法がたくさんありました。
一方で、大きな破れや複雑な修理は、専門業者に依頼するのが賢明でしょう。修理費用は形状や素材によって異なりますが、新品への買い替えと比べるとリーズナブルな選択肢となっています。
カーテンを長持ちさせるためには、日々の丁寧なお手入れが大切ですよ。定期的な掃除や適切な洗濯、破れやすい箇所の予防的なケアを心がけてみましょう。
これらの知識を活かして、ご家庭でのカーテンのメンテナンスに取り組んでみてください。状況に応じて自分で直すか業者に依頼するか、適切な判断ができるようになるはずです。
破れや不具合が気になったら、まずは本記事で紹介した方法を参考に、できることから始めてみましょう。愛着のあるカーテンを長く大切に使い続けることができますよ。