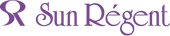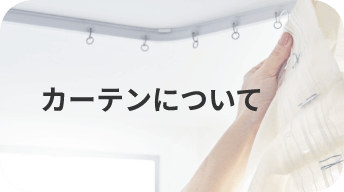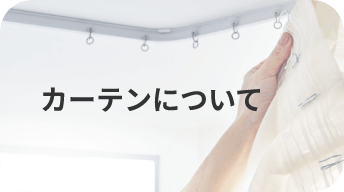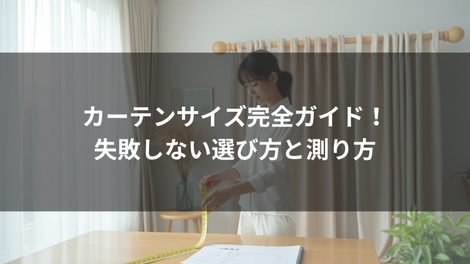Contents
新しい家への引っ越しや模様替えで、ふと気が付くと既存のカーテンが窓のサイズに合わなくなっていた…そんな経験はありませんか?カーテンのサイズ選びは、思った以上に難しいものです。
「前の家で使っていたカーテンを新居で使おうとしたら短すぎて床との間に隙間ができてしまった」「カーテンを購入したものの、幅が足りずに窓枠から光が漏れてしまう」など、カーテンのサイズに関する悩みは尽きないようです。
新居やリフォームで快適な空間を作るためには、窓に合った適切なサイズのカーテンを選ぶことが重要です。カーテンは部屋の印象を大きく左右するだけでなく、プライバシーの保護や冷暖房効率にも影響を与えます。正確なサイズを測り、お部屋に合ったカーテンを選ぶことで、生活の質を高めることができるのです。
この記事では、カーテンサイズの基本知識から正確な測り方、窓の種類別の選び方まで丁寧に解説します。また、遮光や断熱といった機能面でのサイズ選びのポイントや、よくある失敗例とその対処法についても詳しく紹介していきます。
標準サイズのカーテンを購入するか、オーダーメイドカーテンを依頼するか、あるいは既製品を自分で調整するかという選択肢について、それぞれのメリットやデメリットを含めた適切な判断基準をお伝えします。この記事を参考にすれば、あなたの窓にぴったり合うカーテンサイズを見つけることができるでしょう。カーテン選びの失敗を防ぎ、理想の空間づくりを実現するための大切な一歩を、一緒に踏み出していきましょう。
カーテンサイズの基本知識 - 選び方と測り方ガイド

カーテンを選ぶ際には、窓のサイズや形状に合わせた正確なサイズ選びが大切です。一般的なカーテンサイズには既製品で購入できる標準規格がありますが、窓の大きさやカーテンレールの種類によって適切なサイズは変わってきます。間違ったサイズを選ぶと、光漏れやたるみの原因となってしまいます。
カーテンサイズを正確に把握するためには、幅と丈の両方を適切に測ることがポイントです。幅はカーテンレールの長さから算出し、丈は取り付け方法や床からの距離を考慮して決めていきましょう。また、カーテンの表記方法を理解しておくと、ショッピング時に迷わず適切なサイズを選べるようになります。初めてカーテンを選ぶ方も、基本知識を押さえれば失敗なく理想のカーテンを見つけられるでしょう。
一般的なカーテンサイズの種類と規格
日本の既製カーテンには、一般的な窓サイズに対応した標準規格が存在します。幅100cm×丈110cm、幅100cm×丈200cm、幅100cm×丈210cmなどが主流となっており、これらは通常のマンションや一戸建ての窓に対応できるよう設計されています。実際の窓のサイズに合わせるために、カーテンの幅は窓よりも広めに設定されているのが特徴です。
標準規格のカーテンが適している理由は、日本の住宅における窓サイズがある程度統一されているからです。多くのメーカーでは、一般的な日本家屋の窓に合わせた規格サイズを提供しているため、特殊なサイズの窓でない限り既製品で対応可能なことが多いでしょう。
カーテンサイズを理解する上で知っておきたい基本用語として、「片開き」と「両開き」があります。片開きは窓の片側から引くタイプで、両開きは中央から左右に開くタイプです。サイズ表記では「幅100×丈200cm」のように表記され、通常1枚あたりのサイズを示しています。
カーテンサイズは単なる数字ではなく、お部屋の印象や機能性に直結する重要な要素です。窓の大きさだけでなく、カーテンのスタイルや開閉方法も含めて適切なサイズを選ぶことが、美しく機能的な窓辺づくりの第一歩となるのです。
レールの種類と窓の形状による違い
カーテンレールの種類と窓の形状は、適切なカーテンサイズを決める重要な要素です。レールのタイプによって必要なカーテンの幅や丈が大きく変わるため、まずレールの特徴を理解しておく必要があります。
一般的なカーテンレールには、正面付けと天井付けの2種類があります。 正面付けは窓枠の上部に取り付けるタイプで、レールの高さから床までの寸法がカーテン丈になります。

一方、天井付けは天井面に直接取り付けるタイプで、天井から床までの距離がカーテン丈の基準となるでしょう。

さらにレールの形状も重要です。まっすぐな一般的なレールの他に、出窓用の曲線レールや角型レールなどがあり、それぞれに適したカーテンサイズが異なります。特に曲線レールの場合、直線距離だけでなくカーブに沿った実際の長さを測ることが大切です。

窓の形状による違いにも目を向けましょう。一般的な縦長の窓と違い、横長の窓では幅広のカーテンが必要になります。また、アーチ型の窓やまるい窓などの特殊形状の場合は、通常の四角い窓用のカーテンでは対応できないことも。さらに、窓の出っ張り具合(壁からの距離)によって、カーテンレールの取り付け位置やカーテンの丈も変わってきます。
リビングの大きな窓とトイレの小窓ではカーテンの役割も異なるため、同じ考え方でサイズを決めるわけにはいきません。レールと窓の組み合わせによって最適なカーテンサイズは変化するため、実際の測定前にこれらの基本的な違いを把握しておくことが、失敗しないカーテン選びの第一歩なのです。
カーテンのサイズ表記の見方
カーテンを購入する際、サイズ表記の正しい読み方を知ることは大変重要です。カーテンのパッケージやオンラインショップでは「幅100×丈200cm」のように表記されていますが、この数字が実際に何を意味しているのか理解していないと、思わぬ失敗につながります。
カーテンのサイズ表記には基本的に「幅」と「丈」の2つの要素があります。まず幅(Width)は、カーテン1枚あたりの横幅を示しています。例えば「幅100cm」と表記されている場合、そのカーテン1枚の生地幅が100cmということです。両開きタイプのカーテンを購入する場合は、同じサイズのカーテンを2枚用意する必要がありますので注意しましょう。
次に丈(Height)は、カーテンの上部から下部までの長さを表しています。丈の表記はフックの位置から裾までの長さを示しており、「丈200cm」ならフックから裾まで200cmあるということになります。ただし、カーテンのタイプによってはフックを通す位置が変わることもあるため、購入前に確認が必要です。
一般的なカーテンのヒダの呼び方も理解しておくと便利です。例えば「1.5倍ヒダ」「2倍ヒダ」といった表現は、カーテンの生地量を示しています。レール幅の1.5倍や2倍の生地を使用することで、美しいドレープ(波状のひだ)が作られるわけです。
カーテンのサイズ表記を正しく理解することで、窓にぴったり合うカーテンを選ぶことができます。特に既製品を購入する際は、このサイズ表記の意味をしっかり把握して、後悔のない選択をしていきましょう。
正確なカーテンサイズを測る方法

カーテンサイズを正確に測ることは、美しい仕上がりと機能性を確保するために欠かせません。間違ったサイズ選びは光漏れやしわの原因となり、部屋の印象を損ねてしまいます。正確なサイズを測るためには、窓の形状やカーテンレールの位置をしっかり確認することがポイントです。
測定の際はメジャーやカーテンサイズ測定用紙などの適切な道具を用意し、幅と丈を丁寧に計測しましょう。カーテン幅は付いているレールの長さの計測が必要になりますし、丈については窓の形状によって測り方が異なります。これらの基本を押さえて、理想のカーテンスタイルを実現してみてください。
測定前の準備と必要な道具
正確なカーテンサイズを測定するための第一歩は、適切な準備と道具を揃えることです。カーテンの測定に必要な基本道具は、まず「メジャー」が不可欠です。伸縮性の少ないスチール製メジャーか巻き尺を用意すると、正確な長さを測定できます。一般的な布製メジャーは伸びる可能性があるため、精密な測定には向いていません。
測定をスムーズに行うためには、筆記用具とメモ帳も必須アイテムです。各窓ごとの測定値を書き留めることで、後で混乱せずに済みます。特に複数の窓がある場合は、窓の場所や向きも記録しておくと便利でしょう。また、脚立やステップ台があれば、高い位置にあるカーテンレールも安全に測定できます。
測定前には部屋の状態も整えておきましょう。カーテンレール周辺の家具や障害物は移動させ、測定スペースを確保します。現在カーテンが取り付けられている場合は、一度外して測ると正確なサイズが分かりますよ。特にカーテンレールの種類や形状を確認することは重要なポイントです。
適切な準備と道具があれば、カーテンサイズの測定はそれほど難しくありません。この基本的な準備を整えることで、次のステップであるカーテン幅や丈の正確な測定へとスムーズに進むことができるのです。
カーテン幅の正しい測り方
カーテンレールの長さを正確に測ることが、ぴったりサイズのカーテンを選ぶ第一歩です。カーテン幅は単純に窓の横幅ではなく、カーテンレールの端から端までの全長を測定することが重要です。測定の際は、レールの端にある「エンドランナー」の内側から反対側のエンドランナーの内側までを計測しましょう。

カーテンの開閉方法によっても必要な幅が変わってきます。 通常のカーテンサイズを算出にするには、測ったレールの全長から5%程度のゆとりを付ける事で、カーテンを締めた際にゆとりができ見た目が綺麗になります。 両開きタイプ(中央から左右に開くタイプ)の場合は、レールの全長から5%のゆとりを付け、半分に割ったサイズが1枚あたりのカーテンサイズになります。 計算式:測ったレールの全長×1.05÷2=両開きカーテンの1枚あたりの幅サイズ 片開きタイプ(片側だけに寄せるタイプ)の場合、半分に割る必要はない為、レールの全長から5%のゆとりを付けたサイズがカーテンサイズになります。 計算式:測ったレールの全長×1.05=片開きカーテンの幅サイズ
また、レールの種類によって幅の測り方に若干の違いがあります。カーテンボックスがある場合は、ボックス内のレール長さをしっかり測定してください。装飾レールやダブルレールの場合は、それぞれのレールを別々に測ることをお勧めします。
既製カーテンを購入する場合は、カーテンの表示寸法と必要な幅を照らし合わせましょう。例えば「幅100cm×2枚」と表示されている場合、実際のレール長さが180~200cm程度なら適切なサイズと言えます。幅が足りない場合は、3枚以上のカーテンを使用するという方法もあります。
正確な幅を測ることで、光漏れを防ぎ、美しいドレープが作れるカーテンサイズを選ぶことができます。幅の測定は、続いて行う丈の測定と合わせて、理想的なカーテン選びの基本となるポイントなのです。
カーテン丈の測定ポイント
カーテン丈の測定は、窓の種類やお部屋の雰囲気に合わせた仕上がりを左右する重要なポイントです。正確な丈を測ることで、床との隙間やたるみがなく、美しいカーテンスタイルを実現できます。
カーテン丈を測る際は、レールのランナーの位置から必要な長さを基準にします。メジャーをカーテンレールのランナー(フックを差し込む部分)の下端から、垂直に床まで伸ばして測りましょう。

床まである掃出し窓の場合は床まで計測してください。 腰高窓の場合は窓枠の下まで測ると良いでしょう。

測定値にはカーテンの仕上がり方によって調整が必要です。掃出し窓の場合は、一般的には床に対して1〜2cmカーテンを短くすることをおすすめします。 腰高窓の場合は、窓枠の下から+15~20cm程度カーテンを伸ばすと光漏れも防げて見た目も綺麗に仕上がります。 窓の形やデザイン性を考慮して決めると良いでしょう。
測定時は必ず複数箇所を測ることも大切です。古い建物や築年数が経った家では、床が傾いていたり、レールが歪んでいたりする場合があります。左右の端と中央部の少なくとも3か所は測定し、最も短い部分を基準にするとトラブルを防げますよ。
これらのポイントに注意して正確に丈を測れば、窓にぴったり合ったカーテンを選ぶことができます。サイズ選びに迷ったときは、専門店でのアドバイスを受けることも検討してみてください。
掃き出し窓の場合
掃き出し窓にカーテンを設置する場合、床までの長さが重要になります。カーテン丈は床に対する仕上がり方によって印象が大きく変わるため、理想的な長さを正確に測ることが美しい仕上がりのポイントです。
掃き出し窓のカーテン丈を測る際は、カーテンレールのランナー部分から床までを垂直に測定します。測定の際は床が水平であることを確認し、左右と中央部の3か所以上を計測しておくと安心です。古い建物では床が傾いていることもあるため、最も短い部分を基準にすると床に引きずることを防げます。
最も一般的なのは、床から1〜2cm浮かせる丈で、掃除がしやすく実用的です。エアコンの風で揺れても床に触れないため、汚れにくいという特徴があります。
日本の住宅では掃き出し窓の標準的なカーテン丈は200〜215cmが目安ですが、実際には建物によって異なります。必ず実測し、お部屋の用途や雰囲気に合わせた丈を選ぶようにしてみてください。
腰高窓の場合
腰高窓の場合、適切なカーテンサイズを選ぶポイントは窓の形状に合わせた丈の長さにあります。腰高窓は床から60〜90cm程度の高さから始まる窓で、窓下に壁がある形状が特徴です。このタイプの窓に合わせたカーテン丈の測り方は、カーテンレールの位置から窓下の適切な位置までを垂直に測定するのが基本となります。
腰高窓のカーテン丈は、窓枠の下端から15〜20cm程度伸ばした長さが最もスタンダードです。これは視覚的にバランスが良く、窓の大きさを適度に見せる効果があります。
測定する際の注意点として、レールの取り付け位置を正確に確認しましょう。腰高窓では、窓枠上部より10〜15cm高い位置にレールを設置すると部屋が広く見える効果があります。特に天井が低い部屋では、この工夫が有効ですよ。
腰高窓のカーテンサイズ選びで失敗しやすいのが、丈が短すぎる場合です。窓枠ぴったりの長さにすると窓が小さく見えるだけでなく、部屋全体のバランスも悪くなります。かといって長すぎると、特にヒーターがある場合は防火上の問題や汚れの原因になることも。
レースカーテンとドレープの組み合わせる場合、同じ長さにするとすっきりとした印象になります。また、カーテンの裾に溜まりやすいホコリ対策として、床から少し浮かせた長さにするのも一つの方法です。腰高窓向けのカーテンサイズは、機能性とデザイン性のバランスを考慮して選ぶことが大切なポイントとなっています。
出窓の場合
出窓は特殊な形状のため、通常の窓とは異なるカーテンサイズの測り方が必要です。出窓用のカーテンは、出窓全体をカバーできるサイズを選ぶことが重要なポイントになります。最適なカーテンサイズを決めるためには、まず出窓の形状をしっかり理解することから始めましょう。
出窓のカーテンサイズを測る際は、取り付けるレールの形に合わせて測定します。一般的に出窓用のレールは、窓に沿って設置される「L字型」や「コの字型」などの特殊な形状をしています。レールの実際の長さは、単純な直線距離ではなく、カーブに沿った長さを測ることが必要です。専用のメジャーやひもを使って、レールに沿って測ると正確なサイズが分かりますよ。
出窓はお部屋の個性的なアクセントになる特別な空間です。正確なサイズ測定と適切なカーテン選びによって、出窓の魅力を最大限に引き出しながら、機能性も確保できるでしょう。
カーテンの機能に合わせたサイズ選び

カーテンは単なる窓の装飾品ではなく、遮光・断熱・遮熱といった機能性を持ち、その効果を最大限に発揮するためには適切なサイズ選びが不可欠です。遮光カーテンなら光漏れを防ぐために窓枠より大きめのサイズを選び、レースとドレープを組み合わせる場合は互いのバランスを考慮したサイズ調整が必要になります。
特に断熱・遮熱性能を重視する場合は、カーテンと窓枠の間に隙間ができないよう、余裕を持った幅と丈のカーテンを選びましょう。サイズ選びは機能性と美観の両立が鍵となり、使用目的に合わせた最適なカーテンサイズを選ぶことで、快適な室内環境を実現できます。光や熱の調節だけでなく、プライバシー保護にも配慮した選択をしてみてください。
遮光カーテンに最適なサイズ
遮光カーテンの最大の役割は、外からの光を効果的に遮断することです。この機能を十分に発揮させるためには、適切なサイズ選びが不可欠となります。窓枠よりも十分に大きいサイズを選ぶことで、光の侵入を最小限に抑えられるでしょう。
遮光カーテンを選ぶ際は、幅については通常のカーテンよりもさらに余裕を持たせることが大切です。余裕をもたせることで、隙間からの光漏れを防止できます。特に東向きや西向きの窓では、朝日や夕日の強い光を遮るために、この「幅の余裕」が効果を発揮します。
丈についても光漏れ防止の観点から考慮が必要です。通常の床から1〜2cm浮かせる長さか、床ぴったりの長さにすると光漏れを防ぐ事ができます。「アジャスターフック対応」のカーテンを選べば、数センチの丈の調節も可能です。
また、遮光カーテンは厚手の生地が多いため、カーテンレールや装飾レールの耐荷重も確認しておきましょう。特に幅広の窓に取り付ける場合は、レールの強度不足によるたわみが生じないよう注意が必要です。
遮光効果を最大化するためには、窓枠の左右に10〜15cm、上部に10cm程度の余裕を持たせたサイズを選ぶとよいでしょう。このようにサイズに余裕を持たせることで、1級・2級・3級といった遮光等級の性能を十分に活かすことができます。快適な睡眠環境や映像鑑賞のための空間づくりに、ぜひ最適なサイズの遮光カーテンを取り入れてみてください。
レースカーテンとドレープの組み合わせ方
レースカーテンとドレープカーテンの組み合わせは、光や視線のコントロールと室内の美観を両立させる理想的な窓装飾方法です。最適な組み合わせのためには、サイズ選びが重要なポイントとなります。まずレースカーテンは、プライバシーを確保しながら自然光を取り入れる役割を果たします。
レースとドレープを組み合わせる際、丈のバランスをしっかり考慮する必要があります。 レースカーテンは、ドレープカーテンよりも1cm程度短めに設定すると、床に触れて汚れるのを防ぎ、洗濯の頻度も抑えられます。
取り付け方法も効果に影響します。レースカーテンを窓側、ドレープカーテンを室内側に設置するのが基本ですが、二重レールやダブルブラケットを使うとスムーズな開閉が可能になります。特に遮光性を重視する場合は、ドレープとレースの間に隙間ができないよう、十分な幅のカーテンを選びましょう。
カーテンのサイズ選びでは、窓の大きさだけでなく、部屋の雰囲気や用途も考慮することが大切です。リビングなら明るさと視線カット、寝室なら遮光性を重視するなど、空間ごとに最適な組み合わせを検討してみてください。レースとドレープの調和がとれたカーテンは、お部屋を美しく快適に演出します。
断熱・遮熱カーテンのサイズ選び
断熱・遮熱効果を最大限に発揮するカーテンには、適切なサイズ選びが不可欠です。窓枠からの熱の出入りを効果的に抑えるためには、窓枠より大きめのサイズを選ぶことがポイントとなります。具体的には、幅は窓枠より左右に15〜20cm程度、丈は床まで届く丈が理想的でしょう。
断熱・遮熱カーテンは通常の遮光カーテンより重量があるため、カーテンレールの強度も考慮する必要があります。特に幅の広い窓では、レールのたわみを防ぐために強度の高いレールを選んだり、サポート金具を追加したりすることも検討してみてください。
二重カーテンを活用する場合は、レースカーテンとドレープカーテンの間に適切な間隔(約5cm)を確保できるレールを選びましょう。この空間が断熱層となり、より高い効果を発揮します。
断熱・遮熱カーテンを取り付ける際は、カーテンの裾が床に接するか、わずかに浮かせる程度の長さが最適です。カーテンボックスを使用する場合は、上部からの熱の出入りも防げるため、さらに効果的でしょう。
適切なサイズの断熱・遮熱カーテンを選ぶことで、冷暖房効率が向上し、エネルギー消費を抑えられます。快適な室内環境を維持しながら、省エネにも貢献できる賢い選択といえるでしょう。
よくあるカーテンサイズの失敗と対処法

カーテンサイズ選びにおける失敗は想像以上に多く発生しています。幅が足りずに光が漏れる、丈が短すぎて床との間に隙間ができる、逆に長すぎて床に引きずってしまうなど、様々なケースが見られます。こうした失敗は見た目の美しさを損なうだけでなく、遮光や断熱などカーテン本来の機能を十分に発揮できなくなってしまう原因となるのです。
幸いなことに、カーテンサイズの失敗には対処法があります。既製品で合うサイズが見つからない場合は、裾上げやカーテンクリップの活用、レールの付け替えなど様々な調整方法が可能です。また、リフォーム時には窓枠の寸法変更に伴うカーテンサイズの見直しも必要になるでしょう。適切なサイズの選び方と失敗した際の対応策を知っておくことで、理想のカーテン環境を実現できます。
サイズ選びでの失敗事例と解決策
カーテンサイズ選びで最もよくある失敗は、幅の不足です。カーテンを閉めたときに両端から光が漏れてしまうことがあります。これはレール幅を測らずに窓を直接測ってしまったり、レール幅を測った際のメモリの見間違いから起こるケースが多いです。解決策としては、適切なサイズのカーテンを新調するか、足らない分のカーテンをもう1枚追加すると良いでしょう。
次に多いのが丈の失敗です。短すぎると床との間に冷気が入り込み、長すぎると床に引きずって汚れやすくなります。フックの位置を変えるだけで1~2cm調整できるため、少しの丈違いなら簡単に修正可能です。大きく違う場合は、裾上げや裾開きなどの対応を検討してみましょう。
また、窓の形状を考慮していない失敗も見られます。出窓や天井付けレールなど特殊な形状の場合、通常の測り方では合わないことがあります。
カーテンサイズの調整には、カーテンクリップや突っ張り棒の高さ変更などの応急処置も有効です。これらの方法を活用すれば、既製品でもぴったり合うカーテン環境を実現できるはずです。どうしても合わない場合は、オーダーカーテンの検討も視野に入れてみてください。
既製品で対応できないケースの対処法
既製カーテンで対応できないケースは決して珍しくありません。特殊な窓サイズや形状をお持ちの場合でも、いくつかの方法で対処することができます。
まず、既製品で対応できないケースとしては、幅が広い窓、非常に高い窓、変形窓や三角窓などが挙げられます。こうした状況では、オーダーカーテンが最も確実な解決策となりますが、予算や納期の都合でオーダーが難しい場合にも対処法があります。
複数の既製カーテンを組み合わせる方法は、大きな窓に効果的です。例えば、幅300cmの窓なら、100cm幅のカーテンを3枚使用してカバーできます。ただし、ドレープの出方に若干の違いが生じる可能性はあるでしょう。
既製品のサイズを調整する手段としては、DIYリメイクが挙げられます。裾上げテープを使えば、縫製が苦手な方でも簡単に丈を調整できますよ。また、アジャスターフックを使用すれば、丈が少し足りない場合に対応できることもあります。
窓の形状が特殊な場合、代替案としてロールスクリーンやブラインドなどの選択肢も検討してみてください。これらは規格外のサイズにも比較的対応しやすい特徴があります。
予算や時間に余裕がある場合は、カーテンレールの位置を変更するという根本的な解決策も視野に入れてみましょう。レールを上げれば既製品の丈不足を解消できたり、幅を広げれば一般的なサイズのカーテンが使えるようになったりすることがあります。
いずれの方法も、窓の特性や室内の雰囲気、予算を総合的に考慮して選ぶことが大切です。難しいケースでは、カーテン専門店のアドバイスを受けることも賢明な選択といえるでしょう。
リフォーム時のカーテンサイズ調整方法
リフォーム時には窓のサイズや位置が変更されることがよくあるため、カーテンサイズの調整が必要になります。既存のカーテンを新しい窓に合わせる方法と、新たにカーテンを選ぶ際のポイントを押さえておきましょう。
既存カーテンを再利用する場合、まず丈の調整から検討します。丈が短くなった場合は、カーテンフックの位置を上げる方法が簡単です。通常1〜3cmの調整が可能で、手間をかけずにサイズを合わせられます。丈が長すぎる場合は、カーテンの裾上げが必要になるでしょう。専用の裾上げテープを使えば、ミシンがなくても手軽に調整できます。
幅の変更には少し工夫が必要です。窓幅が狭くなった場合、多少狭くなった程度なら既存のものを使っても問題ありません。窓幅が広くなった場合は、サイドパネルを追加する方法が有効。既存のカーテンと色や柄の近い生地を選び、両サイドに付け足すことで対応できます。
リフォームで窓の形状が変わった場合は、カーテンレールの交換も検討してください。例えば出窓から普通窓に変更されたなら、曲線レールから直線レールへの交換が必要となるでしょう。天井高が変わった場合は、カーテンの丈だけでなく、レールの高さも見直す必要があります。
新居やリフォーム時には、窓周りの仕上がり時期を考慮してカーテン購入のタイミングを決めることも大切です。工事完了前に正確なサイズを測ることは難しいため、窓枠が完成してから測定するのが理想的。急ぎの場合は、設計図面からおおよそのサイズを算出し、仮のカーテンを用意しておくという方法もあります。
リフォーム時のカーテン調整は手間がかかりますが、適切に対応することで既存のカーテンを有効活用でき、無駄なコストを抑えられます。大きな調整が必要な場合は、思い切って新調することも選択肢の一つとして考えてみてください。
窓の種類別カーテンサイズガイド

窓の種類によってカーテンの最適なサイズは大きく異なります。マンションの標準的な窓、一戸建ての多様な窓、さらには三角形や円形といった特殊な形状の窓まで、それぞれに合わせたカーテンサイズの選び方があります。窓の位置や向き、部屋の使用目的なども考慮して、最適なカーテンサイズを選ぶことが大切です。
このセクションでは、住宅タイプ別にカーテンサイズの標準的な目安や測定時の注意点をご紹介します。特に建築様式によって異なる窓枠の深さや、窓の開閉方式に応じたカーテンの取り付け位置など、見落としがちなポイントもしっかり押さえていきましょう。適切なサイズのカーテンを選べば、お部屋の印象が格段に良くなりますよ。
マンション標準窓のカーテンサイズ
マンションの標準窓に適したカーテンサイズは、一般的に幅100〜200cm、丈178〜200cmの範囲に収まることが多いです。マンションの窓は建築基準や設計によって規格化されているため、既製品のカーテンでも対応できるケースが多いのが特徴です。
標準的なマンションの窓サイズに合わせたカーテン選びが可能な理由は、建築時の設計が統一されていることにあります。特に新築マンションでは、窓のサイズや位置が間取りごとに類似したパターンで設計されているため、一定の規格内で収まりやすくなっています。例えば、リビングの掃き出し窓なら幅170〜180cm・丈190〜200cm程度、洋室の腰高窓では幅120〜130cm・丈140〜150cm程度が多く見られます。ただし、南向きや角部屋では採光を考慮して大きめの窓が設置されていることもあるので注意が必要でしょう。
マンションの窓にカーテンを取り付ける際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- カーテンレールの位置が窓枠の内側か外側かを確認する
- 窓の結露対策として、レールは窓枠より5cm以上離して設置するのが理想的
- マンションの高層階では強風対策として裾が長すぎないよう調整する
また、マンションの窓には既に取り付けられているカーテンレールがあることも多いため、その種類(アルミレールや装飾レールなど)や形状を確認しておくと良いでしょう。
結論として、マンションの標準窓には比較的規格化されたサイズのカーテンが選びやすく、多くの場合は既製品で対応可能です。しかし、必ず実際の窓とレールの位置を正確に測った上で選びましょう。
一戸建て住宅の窓に合わせたサイズ選び
一戸建て住宅の窓は、マンションと異なり多様なサイズと形状が特徴です。一戸建てでは建築デザインやハウスメーカーによって窓の規格が異なるため、カーテンサイズ選びには細心の注意が必要になります。
一般的な和風住宅では掃き出し窓の幅が180〜200cm、丈が200〜220cmが主流ですが、洋風住宅では出窓や横長窓など多様な窓デザインが見られます。特に注文住宅では完全オリジナルの窓サイズも多く、既製品のカーテンでは対応できないケースも珍しくありません。
一戸建てのカーテンサイズを選ぶ際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 窓の構造や開閉方式(内開き・外開き)を確認し、干渉しないカーテン丈を選ぶ
- 和室の障子や襖との調和を考慮した長さを検討する
- 吹き抜けや高窓には、風によるカーテンのばたつきを防ぐ工夫が必要
一戸建て特有の悩みとして、天井高の違いによるカーテン丈の調整があります。リビングと各部屋で天井高が異なる場合、同じカーテン丈では床からの見え方に差が出てしまうため、それぞれの部屋に合わせた丈選びが必要です。
新築一戸建ての場合は、内装工事段階でカーテンレールの高さや位置を調整できるため、理想のカーテンスタイルに合わせてレール位置を決めるという逆の発想も有効です。吹き抜けのある大開口窓には、電動カーテンレールの設置も検討するとよいでしょう。
一戸建て住宅のカーテンサイズは、住まいの個性に合わせた柔軟な選び方が求められます。標準規格にこだわらず、窓の特徴や住まいのスタイルに合わせたカーテン選びを心がけてみてください。
特殊な形状の窓のカーテンサイズ対応
特殊な形状の窓には、一般的なカーテンでは対応しきれないケースが多くあります。アーチ型や三角形、円形などの特殊窓には、その形状に合わせた専用のカーテン選びが必要です。
特殊形状の窓に対応するカーテンには、主に三つの選択肢があります。一つ目はカスタムオーダーカーテンで、窓の形に合わせて特注品を製作する方法です。二つ目はシェードやブラインドなどの別タイプの窓装飾を活用する方法です。三つ目は既製カーテンの工夫した使い方で対応する方法になります。
半円形や扇形の窓には、扇状に広がるファンシェードが適しています。丸窓には円形専用のブラインドや、窓の上部にロッドを設置して放射状にドレープを広げる方法も効果的でしょう。
傾斜天井付きの窓に対応するには、天井の傾斜に合わせたレール設置が必要です。レールを傾斜に沿って設置し、カーテン丈も斜めにカットすることで美しく仕上がります。この場合、オーダーカーテンを検討すると良いでしょう。
地窓や高窓などの小さな特殊窓には、ローマンシェードやスタイルカーテンが使いやすく便利です。これらは開閉頻度が少ない窓に特に適しています。
複数の異なる形状の窓が並んでいる場合には、統一感を出すために同じ素材や色のカーテンを使用することをお勧めします。素材や質感を揃えることで、異なる形状でも調和のとれた印象に仕上がるはずです。
特殊形状の窓のカーテンサイズを決める際は、まず正確な窓の寸法を測り、その上で専門店に相談することが失敗を防ぐコツです。カーテン専門店では、特殊な窓に対応した提案や採寸サービスも行っていますので、安心して任せられるでしょう。適切なカーテンサイズと種類を選べば、特殊形状の窓も魅力的なインテリアポイントに変わります。
オーダーカーテンと既製品の選び方

カーテン選びでは、既製品とオーダーカーテンの特徴を理解することが大切です。既製品カーテンは一般的な窓サイズに対応した規格品で、比較的リーズナブルな価格と豊富なデザインが魅力です。しかし、特殊なサイズの窓や細かいこだわりがある場合は対応できないことがあります。
一方、オーダーカーテンは窓のサイズに合わせて製作するため、ピッタリと仕上がり、生地や付属品の選択肢も広がります。価格は既製品より高めですが、特殊な形状の窓や大きな窓に対しても柔軟に対応できるメリットがあります。お部屋のイメージや予算、窓のサイズ特性に合わせて、最適なカーテンを選んでみてください。
既製カーテンで対応できるサイズの目安
既製カーテンは手軽に購入できる反面、対応できるサイズには限りがあります。一般的に既製カーテンで対応できる標準的なサイズは、幅が100cm・150cm・200cmの3種類、丈は110cm・135cm・178cm・200cm・210cmといった規格が主流となっています。これらの規格サイズは住宅の一般的な窓に合わせて設計されているため、多くの場合はこの中から選ぶことができるでしょう。
既製カーテンを選ぶ際の目安として、カーテンレールの長さが100cm~200cm、窓から床までの高さが110cm~210cmの範囲内であれば対応可能です。
また、既製カーテンの丈は床からの距離によって選び分けます。掃き出し窓の場合は床に付くか1cm程度浮かせるサイズ、腰高窓の場合は窓枠から15~20cm下がったところまでのサイズが一般的です。多少の誤差であれば、カーテンの裾上げやフックの位置調整で対応できるため、完全に一致するサイズがなくても安心してください。
標準的な規格から外れる窓でも、複数の既製カーテンを組み合わせたり、サイズ調整可能な商品を選んだりすることで対応できる場合もあります。幅広の窓には同じサイズのカーテンを複数枚使用する方法も効果的です。既製カーテンの利点は価格の手頃さとすぐに使える便利さにありますので、窓のサイズが標準的であれば積極的に検討してみてはいかがでしょうか。
オーダーカーテンが必要なケース
オーダーカーテンは特殊な窓サイズや特別なニーズがある場合に最適な選択肢です。既製品では対応できない状況として、まず非標準サイズの窓が挙げられます。幅300cm以上の大きな窓や、100cm未満の小さな窓、天井高3m以上の高い窓などは、既製品のサイズ範囲を超えるためオーダーが必要になるでしょう。
また、特殊な形状の窓にもオーダーカーテンが適しています。三角形や円形、多角形の窓、出窓やアーチ型の窓などは、形に合わせた専用のカーテンが必要です。これらの窓には、通常の四角形を想定した既製品では対応しきれない形状的な課題があります。
高級感や独自性を追求したい場合もオーダーカーテンが適切です。特別なファブリックや希少な素材、複雑なドレープ加工などこだわりの装飾を実現するには、オーダーメイドの自由度が必要となります。室内装飾全体のトーンに合わせた色やテクスチャを厳密に指定したい場合も、既製品では限界があるでしょう。
さらに、建築的な制約がある場合もオーダーカーテンの出番です。天井埋め込み式のカーテンボックスや、特殊な取り付け機構を持つレールシステムには、それに合わせた寸法のカーテンが必要になることがあります。
このように、サイズや形状の特殊性、デザイン性へのこだわり、機能面での特別な要求、建築的制約といった条件が重なる場合には、オーダーカーテンを選ぶことで理想的な窓周りを実現できます。予算や納期は既製品より高めになりますが、長期的な満足度を考えると価値ある投資になるでしょう。
まとめ

カーテンサイズの選び方は、見た目の美しさだけでなく、機能性や快適な住空間づくりの重要な要素です。この記事では、カーテンサイズに関する基本知識から実践的な測り方、窓の種類別の選び方まで幅広く解説してきました。
適切なカーテンサイズを知るためには、まずカーテンの基本的な規格や表記の見方を理解することが大切です。
カーテンサイズを正確に測る際には、専用のメジャーなどの道具を使って、カーテンレールの端から端までの実寸を確認しましょう。特に掃き出し窓、腰高窓、出窓といった窓の種類によって測定方法が異なるため、それぞれの特性を理解した上で採寸することがポイントになります。
また、カーテンの機能面も重要な選択基準です。遮光カーテンなら光漏れを防ぐために適切なサイズ選びが必要ですし、レースカーテンとドレープカーテンの組み合わせ方によっても必要なサイズが変わってくることもあります。
マンションと一戸建てでは標準的な窓のサイズが異なるため、お住まいの建物タイプに合わせたカーテンサイズを選ぶことも大切です。特殊な形状の窓の場合は、既製品では対応できないケースもありますので、オーダーカーテンの検討も視野に入れてみてください。
サイズ選びで失敗しないためには、事前にしっかりと計測し、既製品とオーダーメイドのどちらが自分の窓に適しているかを判断することが重要です。既製品で対応できるサイズなら経済的ですが、微妙にサイズが合わない場合はプロに相談するか、自分で調整する方法も考慮してみましょう。
正確なカーテンサイズを把握し、適切な選択をすることで、お部屋の印象を大きく向上させることができます。この記事の知識を活かして、あなたの窓に最適なカーテンを選び、快適で美しい住空間を作り上げてみませんか。カーテンサイズの「ちょうどいい」を見つけることが、理想の住まいづくりへの第一歩となるはずです。